健康診断で「コレステロールが高い」と言われたら
健康診断で数値が高いと告げられると、不安になる方も多いでしょう。
"コレステロールが悪者"と思われがちですが、実際には体に欠かせない大切な物質です。
まずは、正しい知識を持つことが重要です。

コレステロールとは何か?
コレステロールは細胞膜の構成要素であり、脂質の一種です。細胞膜を強化し、細胞内外の水分調整を助けます。コレステロールは以下のような重要な役割を果たします:
- 細胞膜の強化: 田んぼのあぜ道のような役割。細胞間を埋めて水分の浸透を防ぎます。これにより、細胞内の水分を保持、血管内の水分調整にも寄与します。
- 神経伝達物質の材料: 脳や脊髄に多く存在し、脳内ホルモン、性ホルモン、ビタミンDの原材料にもなります。コレステロールの不足はアルツハイマーやパーキンソン病の原因となることもあります。
コレステロールの生成と調整
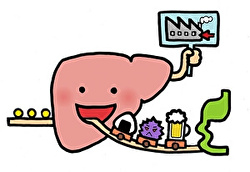
-
体内コレステロールの 約80%は肝臓で生成 されます。
-
食べ物からの影響はごく一部にすぎません。
-
不要になったコレステロールは肝臓で分解され、小腸へ排泄されます。
-
血中濃度は腎臓が監視・調整しています。
👉 つまり「食べ物が直接コレステロールを高くする」のではありません。
善玉・悪玉という“ネーミングの罠”

医療では「善玉」「悪玉」というラベルをつけますが、それは単なる役割の違いにすぎません。
-
LDL(いわゆる悪玉):肝臓から全身へコレステロールを運ぶ。
-
HDL(いわゆる善玉):余分なコレステロールを全身から肝臓に戻す。
👉 最新の理解では、「良い・悪い」ではなく、どちらも必要な輸送システムとして働いていると考えられています。
コレステロールと動脈硬化の関係

心臓は1分間に約5リットル、1日で7トン以上の血液を流しています。
血管は水道管と同じように年齢とともに劣化しやすく、傷ついた部分を修復する材料としてコレステロールが使われます。
血管修復の過程で血栓ができることはありますが、
👉 主な原因は「血管の老化=代謝不良」であって、コレステロールそのものが悪者ではありません。
コレステロールと「水不足」
冒頭で「コレステロールは田んぼのあぜ道のようなもの」と紹介しました。
これは、コレステロールが細胞や血管から水分が過剰に漏れないように守る働きをしているという意味です。
水は体の生命線
私たちの体の約60%は水でできています。
神経伝達、食べ物の消化吸収、関節のクッション作用、そして血液の量や質──。
あらゆる生命活動に水は欠かせません。
水不足が引き起こす連鎖
体内の水分不足が起きると、細胞間で水分の奪い合いが始まります。
-
血液の水分が減る → 血液量が減少し、貧血や高血圧の症状が出やすくなる
-
消化液が減る → 消化不良や便秘につながる
-
細胞自身も必要な水分を確保できず、機能低下を起こす
このように、水分不足は体全体に深刻な影響を及ぼします。
コレステロールの役割
ここでコレステロールが登場します。
コレステロールは「細胞間のあぜ道」として働き、細胞から余分に水分が漏れ出さないように守ります。
そのため、体が水不足を感じると「コレステロール値を上げる」ことで細胞を守ろうとするのです。
つまり、コレステロールの上昇は体からのSOS──水不足のサイン と言えます。
年齢とともに進む水不足
加齢とともに喉の渇きを感じにくくなり、水分摂取量が減ります。
さらに、ジュースやコーヒーには利尿作用があり、薬の多くも強い利尿作用を持つため、年齢を重ねるほど体は水不足に陥りやすくなるのです。
本当に必要な対策
だからこそ、コレステロール値を下げることよりも、まず「水不足を補う」ことが大切。
私たちは、薬草茶に含まれる微量要素とともに、体が必要とする水分をしっかり補うことを提案しています。
それこそが、コレステロール値を自然に整える第一歩なのです。
