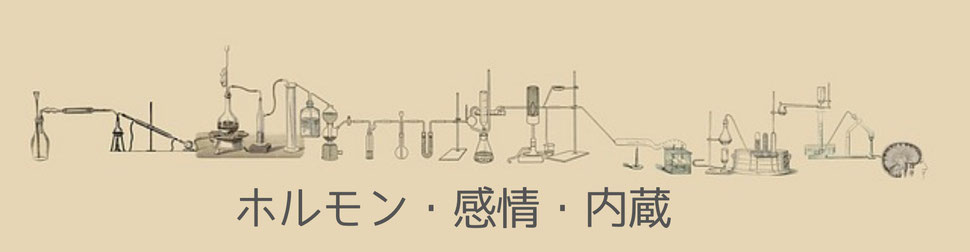「病気を治したい」と願うほど
なぜ病が重くなる?
私たちは病気になると、「治したい」「健康になりたい」と強く願います。
皮肉なことに、この“願い”そのものが、病を深める原因になってしまう。
今回は、その理由を脳の働きやホルモンの仕組みから解説します。
1.脳は否定形を理解できない
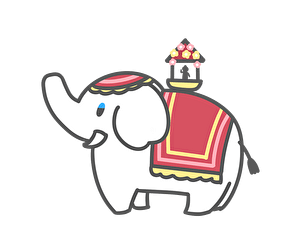
私たちが本当に望む状態をつくるために、まず最初に知っておきたいこと。
それは──
脳は「否定形」を理解できない
という驚くべき事実です。
◆ 「思い浮かべないで」と言われたら?
たとえば、こんな言葉を聞いてみてください。
「白い象を思い浮かべないでください!」
……どうでしょう?
多くの人の脳内には、
“白い象”がはっきりと浮かんだはずです。
これは、脳が「○○しない」という命令を処理できないからです。
脳はまず「白い象」をリアルにイメージしてしまい、
そのあとで「打ち消そうとする」流れになるのです。
◆ 「病気を治したい」の落とし穴
これは、病気との向き合い方にも深く関係しています。
「病気を治したい」と願うとき、脳がまずイメージするのは──“病気の自分”。
そしてそのイメージに、意識とエネルギーが集中していきます。
脳はイメージを現実にしようとする装置
だからこそ、「治したい」という願いが強ければ強いほど、
脳は“病気である自分”をリアルに再現し続けてしまうのです。
2. 欲しいを作るホルモン
ドーパミンの罠
次に注目すべきは「ドーパミン」の働きです。
ドーパミンはよく「やる気ホルモン」や「快楽ホルモン」と呼ばれますが、実は正確には──
「欲しい!やりたい!」と思わせるホルモンです。
たとえば、ある実験では…
ドーパミンが出ないようにされたマウスは、目の前にエサを置いても、まったく食べようとしません。
お腹が空いているのに、動かない。やる気が出ない。
でも、口にエサを入れてあげると──普通に食べます。
つまり…
食欲や快楽ではなく、「自分から何かをしたい」と思わせる“欲求”を生むのが、ドーパミンの本質なんです。
お酒を飲みたいのも、
「過去に味わった楽しさ」が記憶に残っていて、
それをもう一度味わいたいという「欲しい」が生まれるから。
でも、お酒は飲まなくても餓死しませんよね?
つまり本当に求めているのは、お酒そのものではなく、「満たされた感覚」なんです。
3.ドーパミンとエンドルフィンの関係
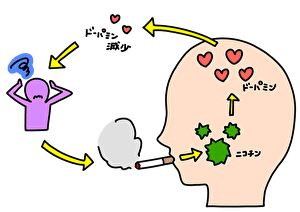
私たちが何かを「欲しい」と感じるとき、
脳内でドーパミンが先ず働きます。
ドーパミンは、
「これが手に入ったら嬉しいな」 「これをやってみたい!」
というような、“やる気”や“期待”を生み出すホルモンです。
そして、その欲しいものが手に入りそうになると──
今度は「エンドルフィン」が分泌されます。
エンドルフィンは、いわば**“脳内のごほうび”ホルモン**。
幸せ、達成感、満足感をもたらしてくれます。
◆ SNSでたとえると…
たとえば、SNSで「いいね」が欲しいとき。
実は、ドーパミンが出ているのは「いいねをもらえるかも」と期待しているときなんです。
「いいねがつくかな?」とスマホを何度も確認してしまうあの感じ──
そのワクワクが、ドーパミン+エンドルフィンのセットなのです。
◆ これを「健康」に置きかえると?
たとえば、あなたが「健康になりたい」と強く思ったとき──
まずはドーパミンが分泌され、「もっと調べよう」「病院へ行こう」と、行動を促します。
ここまでは、良い働きです。でも、問題はここから。
エンドルフィンは「治っていく自分」に対する期待感に反応します。
つまり、情報を集めたり病院へ通ったりする"プロセス"自体に満足感を感じてしまいます。
すると──
-
「もっと情報を集めなきゃ」
-
「もっと病院に行かなきゃ」
-
「もっと頑張って薬を飲まなきゃ」
と、行動そのものが目的化してしまい、
本来のゴールである「健康な状態」から遠ざかってしまうことがあるのです。
◆ 大切なのは「行動のゴール」を見失わないこと
ドーパミンとエンドルフィンは、私たちのやる気や幸福感を支える大切な存在です。
でも、**そのホルモンが何に反応しているのか?**を知っておかないと──
いつの間にか、
-
健康になるための行動が、
-
健康に「なった気がする」ための行動に、
すり替わってしまうことがあるのです。
頑張れば頑張るほど、ストレスが増える
がんばって情報を集めて、色々な治療を試して、努力もしている──
それなのに、理想の健康に近づけない。
この「頑張っているのに結果が出ない」状況が続くと、
私たちの脳と身体には大きなストレスが蓄積されていきます。
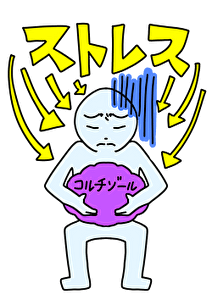
◆ ストレスが続くと、コルチゾールが出る
このとき、体内では「コルチゾール」というホルモンが分泌されます。
コルチゾールは、ストレスに立ち向かうためのホルモン。
-
集中力を高める
-
危機に備えてエネルギーを温存する
-
炎症を抑える
といった働きがあります。
一時的には私たちを守ってくれる大切なホルモンですが、
これが長く続くと、逆に身体に深刻なダメージを与えてしまいます。
◆ 長く続くストレスが、身体を壊していく
慢性的にコルチゾールが分泌されると──
-
免疫力の低下
-
皮膚や内臓の代謝の低下
-
ホルモンバランスの乱れ
-
脳細胞の萎縮
といった悪影響が出てきます。
いわゆる「副腎疲労」や「未病(みびょう)」と呼ばれる状態です。
明確な病名がつかないけれど、
なんとなく調子が悪い…というとき、
このコルチゾール過剰が隠れていることが少なくありません。
◆ 実は、ステロイド薬も同じ原理
実は、こうした「炎症を抑える」作用を人工的に再現したのが、病院でもよく使われるステロイド薬です。
一時的に症状を抑えるにはとても有効ですが、長期的に使い続けると、
本来の自己治癒力を弱めてしまいます。
◆ がんばりすぎが、身体を壊す
情報を集めて、治療をして、努力を重ねる──これは素晴らしい姿勢です。
でも、結果が出ないことに焦り、ストレスをため続けてしまうと、
かえって健康から遠ざかってしまうのです。
つまり、病気を治すために「頑張れば、頑張るほど」ストレスが増え、それにより体の自然治癒力が奪われていくのです。
まとめ
「病気を治したい」──そう強く願うこと自体が、かえって病を深めてしまうことがある。
そんな逆説のような現象が、脳やホルモンの働きを見れば、自然な流れであることがわかってきました。
では、どうすればよいのでしょうか?
◆ 頑張りすぎるほど遠ざかる回復
多くの人は「治そう」と頑張りすぎています。
-
健康情報を探し続ける
-
病院をはしごする
- もっと効く薬を求める
-
食事やサプリをストイックに管理する
…その背景には、
「今の自分ではダメだ」という否定の感情があることも。
でも、それでは脳がストレスモードになり、ドーパミンやコルチゾールの悪循環に陥ってしまうのです。
◆ 回復へのカギは、「受け入れ」と「休息」
真の癒しは、次のような小さな選択から始まります。
-
「病気=悪」と考えず、いまの状態を否定せずに受け入れる
-
頑張るより、まずゆるめる・休む
-
未来の不安より、“今この瞬間”に安心できる環境をつくる
このような心のあり方が、脳や神経のバランスを整え、自然治癒力を目覚めさせます。
◆ 安心と調和を作る『薬草温熱療法』
「健康にならなければ」と焦るよりも、いまの身体をそっと感じて、
体が気持ちよさ、落ち着き、を感じるところを感じ取って、もっと気持ち良くさせてあげる。
これが”薬草温熱療法”です。